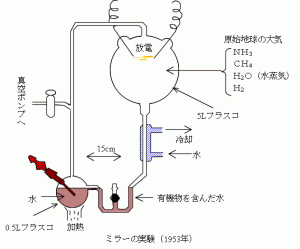地球史と生命誕生仮説の不整合点
生命は、38億年前頃、大気中の放電現象により有機物が生まれ、それが海中で、分子の結合、巨大化を繰り返しながら生まれたというのが、一般的な仮説だ。それは現在と同じような穏やかな海という暗黙の前提の下にある。
そしてこの仮説は、今も教科書に書かれているほど有名なため、最新の地球環境分析からすると、論理不整合であるにもかかわらず、その影響に縛られたままだ。(一部の論理を除く:『生命誕生 地球史から読み解く新しい生命像・中沢弘基著』など)。
どこまでが整合しているのか?
まず、1929年のオパーリンの『生命の起源』は、初めて、無機物から有機物が出来る過程を、論理化し、生命の起源の研究の発端となった。
これ自体は、実験や検証をほとんど伴わない論理だが、それまでの、生命の自然発生説(ダーウィン)やそれを否定する論理(パスツール)の論争を止揚する概念として、大きな役割を果たした。
その後、1953年に、この論理に触発されたミラーが、大気中の雷放電による有機分子の合成実験に成功し、有機分子の大気中で雷放電発生説が出された。
図はコチラからお借りしました。
これは、水、窒素、アンモニア、メタンの混合気体の中で放電すると、アミノ酸の一部が精製されるというもので、現在でも多くの研究の暗黙の前提になっている。
しかし、当時の大気は還元的環境であったという前提から出発したこの論理は、酸化的環境であったとされる最近の研究からすると論理破綻を起こしている。
なぜならば、酸化的環境下では、この実験のような反応は起きず、また、隕石に有機物が含まれていても、それは、酸化的環境では酸化して(燃えて)分解し、無機物になってしまう。
また、これらの説以外にも、常識化しているのが、穏やかな海という暗黙の前提に下で、雷放電により合成された有機分子が自然に寄り集まり(濃縮され)、巨大なアミノ酸やタンパク質などの有機分子が形成されていくという論理でだ。
しかし、大量の水(海)の中に浮かぶ有機分子は、結合より分解するほうが卓越しており、自然に結合を繰り返し高分子化していくことは、化学的にありえない。
これらのことから、生命の起源を考えるには、
- いかにして、現在推定されている酸化的地球環境が、還元的環境になったのか?還元的な環境であれば無機物から有機物が生成するし、生成した有機分子は分解しないですむ。
- そこで出来た、生物の体の前駆体である有機分子が、結合反応を繰り返すためには、すぐ近くに分子が存在する必要がある。そのためには、いかにして構成分子が濃縮されたのかを解明する必要がある?
- 化学反応は一般的に、結合と分解の双方向が存在するが、いかにして結合が卓越するようになったのか?
- 原始地球の環境下では、膨大な宇宙線が降り注いでおり、それに当たれば容易に分解してしまう有機分子は、いかにして存在し続けたのか?
などの疑問を、地球史と整合させた上で、説明できる仮説が必要になる。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.seibutsushi.net/blog/2015/08/3526.html/trackback