2006-06-19
『生命と場所』より…生命観
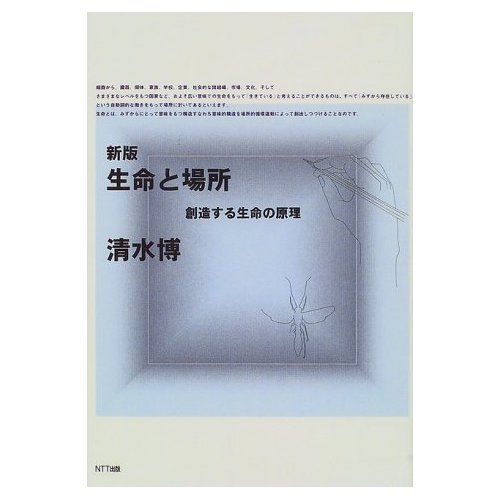
知人に勧められた本=『生命と場所』(NTT出版:清水博著 1992)の序文に、とても共感したので、紹介したい。
004Pより
>新しい時代はまだ完全にその姿をあらわしていないが、地球規模の大きな変革期の今ほど、変化をリードする哲学や思想が必要とされるときはないであろう。その哲学や思想が、生命、さらにいえば「生きているシステム」の深い把握を基盤にして成立するものであることには疑問の余地がない。考えてもみよう。われわれの生命ばかりでなく、そのなかでわれわれの生命を存続させている環境の生命が、かつてこのような危機に直面したことはなかった。この危機の深刻さは、単に量的なものだけでなく、生命の多様性の消滅という不可逆な変化からきている。この危機はまちがいなく、われわれ人間の生きているシステムに関する根本的な誤解と、その上に立った欲望に発している。
>近代がデカルトの「われ惟う故にわれあり」から始まったとすれば、新しい時代は、けっして閉じたものではない人間の生命を深くとらえ、己の姿を再発見することから出発するであろう。
005Pより
>新しい時代の人間像は自他非分離な自己把握によるものでなければならないのだ。その意味では、われわれはまだ人間を発見していないが、同様にさまざまな組織、社会、国家、国際社会などの人間のシステムにも、自他非分離の形で生きていけるシステムに変貌させることを考えていかなければ、環境との調和はありえない。そのためにはまず生きているシステムの本質とは何かを知ることであろう。
さらに、312Pより
>精緻につくられ、理論として完結しているかのように見える近代科学の理論も、実際に適用してみようと思うとさまざまな穴があいているというのが、このごろの私の感慨である。ことに観察や問題の対象と、観察者や問題の回答者のあいだは、ほんとうは分けることができないのに、近代科学の理論では、これを分離可能なものとしてとりあつかっている。その影響を考えていくことが、近代の諸矛盾をのりこえる科学への入り口となる。
引用が長くなってしまったが、この文章を読むと、既存の思想体系としての「科学」は一つのパラダイムに過ぎず、そのパラダイムは行き詰まりを迎えているのだということにあらためて気付かされる。
既存のパラダイムにしがみつき権威を維持しようとする学者と、パラダイム転換の必要を強く感じる学者や人々の間の認識の差を埋めるのは大変だ。現在の科学にしても、旧い時代のパラダイムや現在の学界の権威に基づく認識バイアスがかかった結果存在している。旧いパラダイムから新しいパラダイムへの転換期として現在の「科学」を俯瞰する視点も重要かもしれない。
デカルト以来の“近代思想”の影響を色濃く受けた、“人間”および“観察主体”(自我)に絶対的価値を置く近代科学から、対象世界と同化した「自他非分離」の新しい世界の捉え方へと脱皮しない限り、「科学」は人類と世界を滅亡に導く道具になってしまう、ということを筆者の清水氏は危惧しているのではないだろうか。
人類も生物の一種(生命の原理は人類にも適用される)であり、しかも“近代自我”という人間が勝手に作り出した幻想が、対象世界を客観的に把握などできるはずがないということはもはや自明であり、この旧いパラダイムから抜け出した新しい対象世界把握・生命把握が必要だと思う。しかし、21世紀になって数年経つ今になっても、そういう可能性のありそうな思想や哲学や科学が一向に現れてこないのはなぜなのだろうか。
近代思想(人間第一主義や主体としての自我の肯定)という非科学的な(まるで根拠の無い)固定観念の縛りは、「科学」に思ったよりも深刻な影響を与えているのかもしれない。
このブログを読んでいただいて、応援してもいいかな~と思った方、
ぜひ、下のリンクにとんでください!よろしく~^^;)
↓
☆人気blogランキングへ☆
FC2 Blog Ranking
「脳は他者の怒りや恐怖を無視できない」

今日は、ワーヤード・ニュースから^^)
http://hotwired.goo.ne.jp/news/technology/story/20050127303.html
>怒った声を聞くと、脳の中で音声認識に関連する部分である上側頭溝の働きが活発になることがわかった。
>被験者に対して、一方の耳から聞こえてくる怒鳴り声は無視し、もう一方から聞こえる普通の声に意識を集中するよう指示した時でさえ、fMRIの映像では上側頭溝が活発に働いていた。
>脳は重要な情報を含む可能性がある感覚信号を優先し、他のことに没頭していた心にも、その信号を伝えているということになる。
めっちゃ心当たりありますね~。
職場で誰かが怒られていたり、不機嫌な感じの人がいたりすると、思わずなんかギクっとしたりいやな空気になったりしちゃう。
後ろ向きの人が一人でもいると、周りみんなの気が重く沈んでしまう。
人間の同化能力のすごさを物語ってる現象ですね。
自分のことしか意識に無く、平気で不機嫌になったり、ヤル気なくダルそうにしている人は、それが周りの活力をいかに下げているのかを認識した方がいいですね(自戒もこめて^^;)。
自分へこだわりを捨てて、周り人の脳を元気にする人になりたいものです。
応援してくれる方、ぜひ押してくれろ~^^;)
↓
☆人気blogランキングへ☆
FC2 Blog Ranking
細胞内での連続共生説(初稿)
(初稿)2008.07.30
科学者が、論理整合性を堅持するために書く論文に比して、一般の素人向けの書籍は、著者の肩の力が抜けた分、その人となりが見えてきて、面白いことがあります。例えば、福岡 伸一著の「生物と無生物のあいだ」などは、(顔写真とは似つかわしくもない?)美文に読み耽ってしまったりもします(爆)。
同様に、リン・マーギュリス女史の「共生生命体の30億年」の出だし部分も、文章から垣間見れる私生活場面ではオマセで一途で悩み多い出会いと結婚や、息子との自説をめぐる応答の中に、人物像と研究者としての原点が見えてきて、ちょと好感が持てたりします(笑)。でも読み進むと、やっぱり奥付の写真のように、顔は微笑んでいるけど腕を組んで攻撃的ないかり肩が見えてきたりもします(爆)。
一般に認知されつつある共生説との違いや、自説に都合の良い概念や状況証拠(?)が展開されていますので、その内容を紹介したいと思います。
■1世紀を経て、その検証の時期を迎えた、という「共生説」
—————————————-
◆共生:1873年/アントン・ド=バリは、「異なる名称をもつ生物が一緒に暮らすこと」と定義した。
—————————————-
◆共生発生:ロシアのコンスタンティン・メレシコフスキー(1855~1921)が提唱した概念。
(*共存が長期にわたると、場合によっては、新しい体や器官や種が出現するという共生発生が起こる、というもの。)
—————————————-
ということですから、まさしく、100年以上を経て検証の時期にあるといえるでしょう。
■連続細胞内共生(SET)説:リン・マーギュリス
「連続」という言葉は、一運の合体に順序があることを指しており、「共生発生が真核細胞の起源である」というマーギュリスの説は、四つの過程があります。そして、その四つにはすベて細菌が関係する、といいます。その慨念のあらましとは、
====================
◆発酵性「古細菌」と呼ばれ、硫黄と熱を好むタイプの細菌が、遊走性の細菌と一緒になり、一体化して、動植物や菌類の細胞の祖先細胞の基本となる核を含む細胞質を構成した。この原初の遊走性プロチスト[狭義の原生生物で、多くは単細胞]は嫌気性である。
◆有糸分裂をするようになった遊走性のプロチストに別のタイプの自由生活微生物である酸素呼吸細菌が組み込まれた。この酸素呼吸性の三者(好熱好酸菌、遊走性細菌、酸素呼吸細菌)の複合体は、微粒子状の食物をのみこめるようになったので、大きくて複雑な細胞が生まれた。〔約20億年前:遊走能と酸素呼吸能をもつ真核細胞の登場〕
この第二の合併体、すなわち酸素呼吸能を獲得した遊走性の嫌気性菌は、三つの構成要素をもち、大気中に蓄積した酸素に対処できる細胞になった。小さな遊走性細菌と耐酸性や耐熱性の嫌気性菌と酸素呼吸細菌の三つからできたこの細胞から、数々の動植物が生まれることになる。
◆複合細胞が生まれた一連の合体の終わりに、真核細胞のうちのあるものが緑色の光合成細菌をのみこみ、消化しそこなって(=細胞内での闘いのすえに)体内に残した緑色細菌は葉緑体になった。つまり、日光を好み光合成ができる緑色細菌が第四のパートナーとして完全に一体化した。
この最後の合体で生まれた遊走性の緑藻が、今日の植物の祖先である。
真核細胞の細胞質にある遺伝子は「裸の遺伝子」ではなく、細菌の遺伝子に由来するという考えで、細胞の基本となる細胞質は核も含めて嫌気性細菌の子孫だとする。
====================
マーギュリスは、連続細胞内共生説(SET)が主張する四つのうちの三つまでを同定できる、としています。つまり、
◆ステップ1):細胞の基本となる細胞質は核も含めて嫌気性細菌のものであり、
とくにタンパク質をつくる代謝の大半は、好熱好酸性細菌に由来する。
◆ステップ2):『?』
◆ステップ3):真核細胞内で酸素呼吸をするミトコンドリアは、「紅色細菌」あるいは
「プロテオバクテリア」と呼ばれている細菌が共生したものだ。
◆ステップ4):葉緑体その他の色素体は、かつては光合成シアノバクテリアだった。

![]()

==========
争点は、「ステップ2)」ですが、生物学者一般は内因説を支持しているようです。
====================
◆内因説あるいは直接派生説:1970年代前半
ブリティッシュ・コロンビア大学 マックス・テイラー
トム・カヴァリアースミス
真核細胞の起源について、直接派生説では三種類のオルガネラ(ミトコンドリア、繊毛、色素体)は核から「摘み取られた」DNAから生じたもので、外来の細菌由来ではないという見解。
====================
直接派生はマックスが理論として考え出したものだそうですが、生物学者一般の暗黙の前提となっている分化による進化という概念と一致している、というものです。
しかし、マーギュリスは、「繊毛、精子の尾、感覚突起、そのほか数多くの真核細胞の付属物が、嫌気性菌と遊走性細菌との融合から生じた。」との視点に立ちます。
> 中心小体/キネトソームになった外来者には、いまも自由生活をしている親戚がいる。細菌の一種、スピロヘータである。スピロヘー夕の祖先であるくねくね動く乱暴者たちは、空腹のあまり死にものぐるいで多くの古細菌につっこんでいった。侵入された古細菌のなかには、今日のサーモプラズマに似たものもあった。侵入のあとに停戦がきた。私はスピロヘータと古細菌が合体した状態で生き残り、最古の真核細胞が生まれたのだと思う。【中略】
> そこで何が起こったか。つねに乾燥や食物不足や有害物などの潜在的な災難にさらされている外に比べれば、細胞内環境は水分と栄養分に恵まれたところだ。古細菌の細胞膜という障壁を突き破ったスピロヘータ(あるいはそのほかの遊泳性の細菌)は、常にエネルギーと食物を享受できることになった。
> 襲撃したものとされたものの増殖のしかたはしだいに関連してきた。生息の拠点となる元の細胞を制圧してしまったのでは、襲撃者も長くは生き延びられない。襲撃者は共生体となり、時の経過とともにオルガネラとなったのである。合体のあと新しい生き残りの策略が生まれたのだ。
> 私は、くねくねと動く酸素に弱い細菌が食物を求めて古細菌を襲い、侵入していった場面を心に描く。動く細菌にすみつかれた古細菌は、そのおかげで速く動けるようになった。真核細胞は、「染色体のダンス」と呼ばれる有糸分裂をするが、これこそスピロヘータのたえまない動きに由来する。
と展開すします。このあたりの内容は、2008年06月22日のなんでや劇場91「生物史から学ぶ自然の摂理⑪ 生命の基幹システムを探る~タンパク質の多様なはたらき~」でも取り上げられました。
マーギュリスは、最初はスピロヘータが古細菌に付着するための構造をつくったのだが、その付着部が、スピロヘータと古細菌の「共生発生的な統合の結果、今日の中心小体/キネトソームになったのだ」、と捉えています。それゆえに、マーギュリスらは普通の生物や細胞小器官にはあまり見られずスピロヘー夕や繊毛にだけ共通して存在する核酸やクンパク質を探している、といいます。
====================
◆エネギュイ=レンホセック説:1898年/L・F・エネギュイ
ミハリー・フォン・レンホセック
彼らが、動物細胞の中心小体とキネトソームか同じものであることに気づき、有糸分裂のあと中心体が極から移勣してキネトソームになるという考えを提示した。この説は彼らの死後に、電子顕微鏡の所見によって証明された。
→マーギュリスが「中心小体/キネトソーム」
という二重の名称を使うきっかけになった。
====================
⇒キネトソーム(Kinetosome)
オクスフォード大学のデイヴィッド・C・スミスは、真核細胞内に存在する、スピロヘー夕共生体の名残と思われるものを「この微生物は徐々に自分の部分を失い、ゆっくりと背景に溶けこんでいったが、遺物がもとの姿をしのばせる」と表現したそうです。なにやら、三木成夫氏が「ヒトのからだ――生物史的考察」の中で、
> これにくらべて、個体発生ではすべての過程が連続的に追求できるという利点があり、しかも“個体発生は、宗族発生をくり返す(ヘッケル)”という先人の言葉にもあるように、てっとり早く、生物分化の歴史がながめられるがのごとくである。
> しかし実際にそこに再現されるものは、宗族発生の歴史そのものではなく、いわば歴史の“おもかげ”であって、しかも、このつかみどころのないものが走馬灯のごとくに過ぎ去るのである。
と述べていることを彷彿とさせるではありませんか! それはまた、
>歴史的に形成されてきた存在は(=進化を重ねてきた存在は)、生物集団であれ人間集団であれ、全て始原実現体の上に次々と新実現体が積み重ねられた、進化積層体(or 塗り重ね構造体)である。 (リンク)
とも、さらにオーバーラップしてきます。摂理を極め透徹した洞察力に富む賢人たちの潜在思念には、それぞれに通ずるものがあるということでしょうか?
—————————————-
精子の尾や、繊毛虫の繊毛、女性の卵管細胞、喉にある繊毛、有糸分裂のときに染色体を引っ張る微小管も、輪切りにすると独特の同じ構造(=九組の微小管からなる)をしているのは確からしいです。状況証拠はあるのですが、運動系の蛋白質の起源としてスピロヘータを特定するだけの事実の解明には至っていないと、いいます。
翻訳者である中村桂子氏が藻類の進化を調べた結果、細胞が一緒になったり、DNAがあちこち動き回ったりすることを実証したと云いますが、続けて曰く、
>少なくとも、私たちのような多細胞生物をつくる細胞が出来上がるところまでの進化は、これまで考えられていたように遺伝子に変異が起きて、その中から環境に合ったものが選択されるというイメージよりははるかにダイナミックなDNAの動きで新しい種が生まれたということは紛れもない事実と言ってよいと思う。(「訳者あとがき」より)
これらの事実関係を紡いでいけば、原生生物の「細胞内の連続共生説」には、同意できそうです。
出典:「共生生命体の30億年」リン・マーギュリス著/中村桂子=訳
関連参考サイト:原生生物の進化
by びん
