2013-07-24
アインシュタイン、その光と影 3
『光速度は発光体や観測者の運動にかかわらず常に一定・不変である』~これはアインシュタインが語った認識の中でも最も有名なものですが、今日はこの認識を切開して行きたいと思います

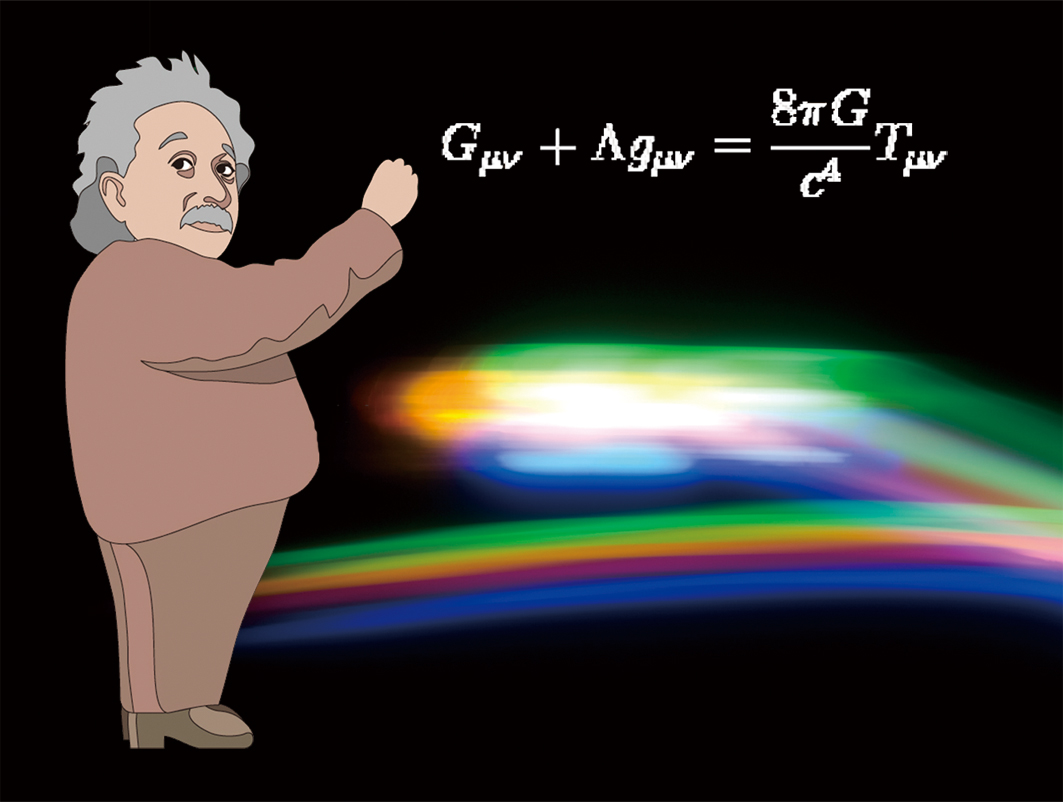
古代以来光の速度は無限大だとずっと信じられてきましたが、光の速度に初めて着眼したのはガリレオ(1564-1642)だと言われています。しかし実際に光の速度の計測に成功したのは(それから100年以上経った)今から300年ほど前でした。デンマークの天文学者レーマー(1644-1710)が木星とその衛星イオの周期の差から導いた1676年の21万4,300km/sが最初の光速の数値です。その後19世紀のフランスのフィゾーの実験によって光速は31万3,100 km/sに修正され、20世紀以降の精密な計測を経て、真空中の光の速度は1983年の「国際度量衡委員会」で29万9792.458km/sとすることが決められました。
応援よろしくお願いします

ところで、アインシュタインが“光速度は一定・不変”を提起したのは1905年ですから、すでにその当時、光の速度には概ね30万km/sという有限値があることが認められていた訳です。アインシュタインは『特殊相対性原理』の論文の中で、走っている電車の中での光の速さとボールの速さを取り上げ、それらを電車の中にいる人と電車の外で静止している人が見た場合にどうなるかを比較して理論の構築を進めました。もともと、光とボールの速度を比較するという発想は、光の粒子としての性質に着目してのことですが、『粒子派』の代表格がニュートンとアインシュタインであることは前項(コチラ)で書いたとおりです。
一方、光には波の性質もあります。実は19世紀後半はむしろ「光は波である」という捉え方の方が遥かに優勢でした。アインシュタインはこの見方に異議を唱えたとも言えますが、彼の表現には一流のトリック性も垣間見えるような気がします。
そこで、今日は光の速度を弾丸・音・水と比較してできる限り正確に光の特性を明らかにしたいと思います。
【なお以下に掲載した図はコチラからお借りしました】
まず、物体や波を動かしている源(=以後ソースと呼びます)が等速運動している場合からまとめます。下図は鉄砲を持った人が走っている場合ですが、弾丸の速度には鉄砲の速度が足されます。
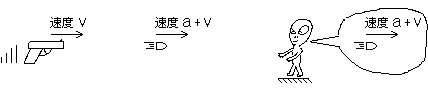
では動いているスピーカーから音波が飛び出してくる場合はどうでしょうか?。スピーカーの速さは音波の速さに足されません。
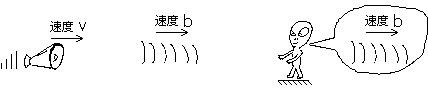
念のために水の波についても見てみましょう。クジラが観測者に向かってきても、クジラの速さはクジラが立てる波の速さに足されません。
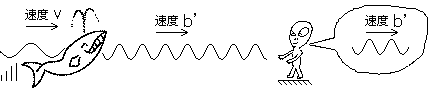
さて、ストロボから飛び出す光についてはどうかと言うと、音波や水の波と同じでストロボの速度は足されません。
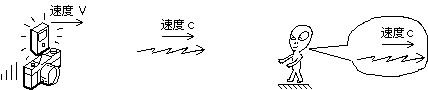
以上を要約すると、物体の速度にはソースの速度が加算されますが、音・波・光にはソースの速度は何の影響もないことがわかります。
では次に観測者が等速運動している場合を整理してみます。
鉄砲から速度 a で飛び出してくる弾丸に向かって、観測者が速度 u で走っていったとしましょう。彼が見るものは速度a+uで向かってくる弾丸です。
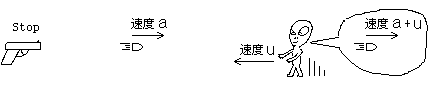
スピーカーから速度 b で飛び出してくる音波に向かって、観測者が速度uで走っていった場合はどうでしょうか?。やはり彼が見るものは速度b+uで向かってくる音波です。
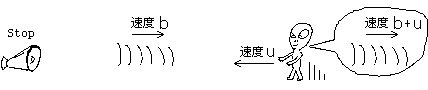
最後は光です。ストロボから速度cで飛び出してくる光に向かって、観測者が速度uで走っていくと、何と!彼が見るのは(uの足されない)速度cで向かってくる光です。
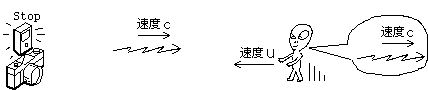
弾丸でも音波でも(つまり物体であれ波であれ)共通に観測者の速さが足されたのに、光だけは観測者の速さが足されないのです。特に、同じ波に属する音波などと異なる結果になる点は大変不思議な現象と言えます。
どんなに奇妙な現象でも、現実に起こっていることであれば認めなければならないというのが物理学の基本ルールですから、この点はその後徹底して追試が行われました。精度を上げながら20世紀後半まで続けられた光の速度の実験結果は、例外なく光の速さが変わらないことを支持するものでした。そして今日では、光源や観測者の速度によらず定まった値をとることを誰もが認めています。なぜそうなるのかは未だにわかっていませんが・・・。
もっとも、アインシュタインが論文を発表するよりもさらに約20年前、後に“失敗したことで有名になった実験”と称されるようになった1887年の「マイケルソンとモーレーの実験」で、光は光源や観測者の速度によらず定まった値をとることはすでに示唆されていました。また電磁気学の分野では、マックスウェルの方程式などから十分に予測されていました。したがって、仮にアインシュタインが登場しなくても、“光の速度は一定かつ不変”という認識は他の誰かが提起しただろうと言われています。
ここまで述べてきたような光の性質を現在の日本では『光速度不変の原理』と呼んでいます。そこには、理由がはっきりしないにもかかわらず、あらゆる実験・実測の結果が大変な正確さで証明されている以上、ひとつの真理として信用して他の理論の「よりどころ」にするという意味も含まれています。ただし、この呼び方は、初学者の誤解を招く疑いがあるという理由で、英文での表記 Constancy of the Velocity of Light に倣って「光の速さの定数性」と呼ぶことを推奨する科学者もいるようです。
さて、アインシュタイン・シリーズの第3回目は如何だったでしょうか?。
『“光速度不変”は不思議?それともあたりまえ?』という本日のテーマに立ち返って言うなら、ソースの運動状況の影響を受けないのが波動であるという点は、言わばあたりまえかな?と思いますが、観測者の速度によって大半の波動が見かけの速度が変わるのに、光だけはその影響を受けないという点は大変不思議だと感じました.。宜しければ、ぜひ、読者の皆さんからの意見もお聞かせください。
この記事で「なぜそうなるのかわからない」と書いた部分もおいおい明らかにしたいと考えています。それでは次回もお楽しみに

by 管理人
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.seibutsushi.net/blog/2013/07/1400.html/trackback
