2胚葉生物 クラゲ
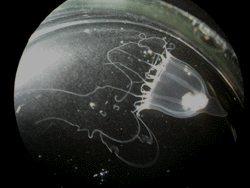
無胚葉生物であるカイメンから1次元進化し2胚葉生物になったのがクラゲ。
クラゲの体細胞の機能分化を調査しました。
以下「多細胞生物の機能分化」 リンク にある分類に沿って整理してみます。

![]()

◆神経系
頭や脳も無く神経細胞は網の目のように体全体に分布しています。
このような神経系は散在神経系と呼ばれています。
クラゲやイソギンチャクなど刺胞動物はエサを求めて動きまわるということはあまりありません。
リンク
◆感覚器
多くの種類では傘の縁に触手がある。また、ヒドロクラゲ類では触手の付け根に眼点(光受容(特に走光性)に関係する構造体)を持つものがあるほか、傘の縁に平衡胞(重力や力のかかる向きを知ることである、ヒトでは内耳がこれに当たる)を持つものもある。
リンク
◆運動器
口腕
口の中央から伸びる4本の足みたいなもの。
餌をとりこむ時につかう部分で、人間で言うと唇。
メスは基本部が花弁状の保育嚢となる。
リンク
◆消化器
胃腔
傘から透き通って見える、4つに分かれている部分が胃。
簡単な袋状。
透明だから、餌が溶かされていく様子が外から見える。
リンク
◆循環器?
水管
放射管とも言う。
白いしまみたいな模様(体が透明だから肉眼でも分かる)。
じっとしているとき、傘の縁を、パフパフ動かしている。
それは、体液や栄養を水管に送り込んでいるための行動。泳ぐためではない。
このことを、パルセーション(開閉運動)という。
水管の内部には、せん毛があり、傘の閉会運動が無くても、体液や栄養を少しずつ循環している。
リンク
◆生殖器
生殖巣
4つある。
成熟すればするほど立派になる!
薄紫色・赤褐色・ピンク・白など、いろんな色がある。
ここでオスは精子、メスでは卵子が作られる。
リンク
以上のように、呼吸器、泌尿器、内分泌器を除いた機能をクラゲは保有している。
なおクラゲ(刺胞生物)の特徴である刺胞細胞について補足すると・・
刺胞とは,餌をとらえたり,身を守ったりする際に使用され,この動物の仲間にとって,なくてはならない非常に重要なものです。これは,刺胞細胞によってつくられる細胞内器官で,カプセル状の構造をしています。カプセルの大きさはだいたい10-100umと非常に小さく,肉眼では見えません。このカプセルの中には,毒液と管状の刺糸とよばれるものがコイル状に折りたたまれています。なんらかの刺激を受けると,この刺糸が反転して翻出し,相手(餌や敵)にカプセル内の毒を注入しますが,刺胞のタイプによっては単に巻き付くだけものものなどもあります。刺胞はその形状から大きく20タイプほどに分類されていおり,どのタイプの刺胞を持つかは,分類群によって,また,体の部位によって異なっています。
刺胞は,非常に小さい上にその構造も著しく複雑なことから,生物のつくる精巧な構造物の極致といわれています。
リンク
※刺胞とは独立した細胞ではなく細胞内器官です。これは1世代前のカイメンには見られません。この刺胞をこの段階でどのように獲得していったのか、またそれ以降の生物にどのように継承されたのかについて、興味をもちました。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.seibutsushi.net/blog/2008/03/413.html/trackback
コメント2件
yama3 | 2008.04.12 19:02
さんぽ☆さん、遅レスすいません。マクロファージが情報伝達物質を使って判断しているところまでは分かったのですが、今回の調査では「くっついたりはなれたり」というぐらいまでしか分かりませんでした(><)「同類認識」と「情報伝達物質」の関連は引き続き調べていこうと思います。
PS健康法のアドバイスありがとうです。頭ぐりぐりやってみます。

>疲労した体細胞は酸化的傷害を受けて、マイナス電荷を帯びている
それをマクロファージが感知して死んだ細胞等を食べているんですね!!
死んだ細胞をどう見分けているのかは分かったのですが、それ以外(病原菌等)はどう見分けているのでしょうか?
同類だけ見分ける機能があって、それ以外は何でも食べるということであっていますか?
よかったら教えて下さい~☆
P.S
肩こりは、頭のこりからきていることもあるので、頭をほぐす(頭を床にボールを転がすようにゴリゴリなすりつける)のも効果ありますよ。